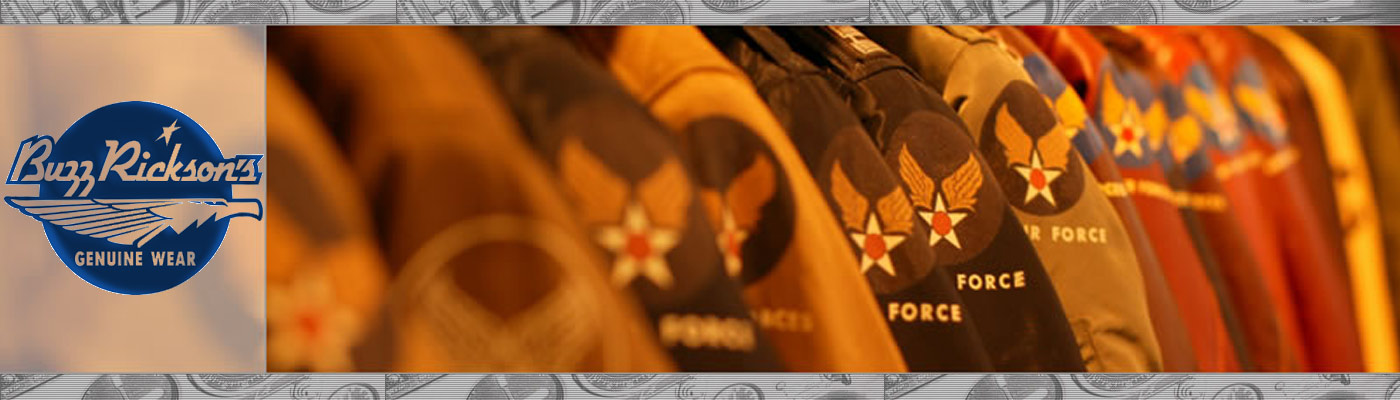ITEM SEARCH▲ OPEN / 開ける
WAREHOUSE (ウエアハウス) デニム(チノパンなど)
lot-1333 :WAREHOUSEウエアハウス 1910~1915 No3 WAIST OVERALLS デニム ジーンズ lot-1333
★6.2番&5.5番×10番 NO.3セルヴィッチデニム
インディゴデニム
★鉄製タックボタン
★鉄製バックル
XX,NO2、そして「NO:3」
この知られざるジーンズの謎に迫る。
数年しか製造されていないその幻の「333」を生地から徹底再現。
1911年から1915年まで製造されていた通称「No3」シリーズ。当時のカタログにはXXシリーズや「No2」と同じように、シャツやブラウスも掲載されている。縫製糸にイエローやオレンジではなく共糸(濃紺)が使用され、バックヨークや飾りステッチが無いなど、このシリーズにだけ採用されたディテールが随所にある。とはいえ、これらが展開されたのはまだアメリカでは量産体制が整わない第一次世界大戦直後の時代、縫製仕様はむしろ「頑強」といえる箇所もみられるのだ。当時同じエリアに存在したワークウエアブランドであるノイシュタッターブラザーズやハイマンの仕様に近いディテールも見られるため、そのゾーンを意識した「ワーク色」の強い存在といえるのではないだろうか。ごく限られた年数しか生産されていないため、当然のごとくその実存数はXXとNO2よりも極めて少ないのである。
当時のデニムを供給していたのはアモスケアグで、同社がすべてのデニムを担っていたとするならば、
XX,NO2,NO3のグレード付けをどのようにしていたのだろうか。それはデニムの番手にヒントがあるのかもしれない。NO3のデニムの番手を分析した結果、タテ糸は6.2番&5.5番という太い糸が使用されていた。
1910年代の紡績技術を考えると、細い番手を作ることはまだ困難であった時代といわれている。
糸の番手や緯糸の打ち込み本数がそのグレードを決める要素になっていると考えられる。生地、縫製に変化がついた個性的なグレードがこの「NO3」といえるだろう。
フロントのポケットカッティングがNO3のみに採用されているカッティングで、コインポケットは外つけではない。また、同時代は5ポケットにはじめて環縫い(チェーンステッチ)が使用されたものであり、
尻部分の縫い合わせには巻き縫いが使用されている。バックヨークはなく、ウエストバンドが付くのみのシンプルなバックスタイル。前たてには二本糸のオーバーロックが使用されるが、ロックミシンもこの時代から使用が始まっている。デニムは経糸が極太で、緯糸には細番手といえる10番を使用しているため、表面には凹凸が顕著にみられ、ヴィンテージ同様、意外にもヘヴィオンスの触感だ。縫い糸はインディゴに合わせた共糸である濃紺が使用されており、イエローやオレンジが使用されるものとは全く違うシックな佇まい。
バックポケットの飾りステッチも入らないため、強いブランディングを感じない異色な存在と言えるだろう。